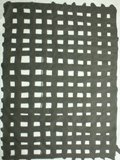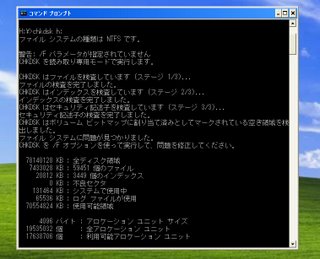Had lunch at a Turkish restaurant nearby. There was my favorite Peruvian restaurant there, and I've felt pity its close. Anyway, here opens another international cuisine to entertain my belly :)
Had lunch at a Turkish restaurant nearby. There was my favorite Peruvian restaurant there, and I've felt pity its close. Anyway, here opens another international cuisine to entertain my belly :)新しくできたトルコ料理レストランに行きました。少し前まで、ここは大好きなペルー料理レストランでした。閉店してしまったのは残念ですが、新しいレストランとも仲良くなりたいな。
 There are several set menus for lunch. I selected Etli Nohut (stew of garbanzo beans, beef and tomato) and Beef Kebap(BBQ), along with bean soup, turkish bread, salad and turkish tea.
There are several set menus for lunch. I selected Etli Nohut (stew of garbanzo beans, beef and tomato) and Beef Kebap(BBQ), along with bean soup, turkish bread, salad and turkish tea.ランチは定食が数種類。私のメインはひよこ豆の煮物とカバブ。まず、豆のポタージュ。レモンの風味が新鮮でおいしい。添えられたトルコのパン・エキメキは、ぱりぱりの食感と塩味が何だかヨーロッパ風でした。
 The main course had much amount. I liked the stew espceially. I am sure it goes well with wine.
The main course had much amount. I liked the stew espceially. I am sure it goes well with wine.メインの煮物は、かなりのボリュームでした。食いしん坊の私がそう思ったくらいなので、一緒した同僚はきっと・・・。ひよこ豆の煮込みが、やさしい味でとてもよかったです。この煮物とワインで夕食っていうのもよさそう。カバブは、シンプルな味つけと、しっとりした食感がよかったです。
 I also enjoyed the bitter taste and flavor of Turkish tea. I wonder this every time I have the Turkish tea: Why is the hot tea served in a thin glass cup?
I also enjoyed the bitter taste and flavor of Turkish tea. I wonder this every time I have the Turkish tea: Why is the hot tea served in a thin glass cup?最後に、トルコの紅茶が出てきました。苦くておいしかったです。私は砂糖を入れませんでしたが、ほんとうは入れたほうがいいのかもしれません。トルコの紅茶をいただく度に「なぜ、熱々の紅茶を薄いガラスのカップで飲むのか」不思議です。
さて。お店情報です。
名前:ケレベッキ(トルコ語で蝶のこと)
場所:沖縄県西原町翁長 558-2-101
電話:098-944-4747
営業時間: ランチ11:30am-3pm、
ディナー5:30pm-11pm(金・土・祝前日は0amまで)
定休日:水曜日
By the way, let me introduce another Turkish restaurant in Tokyo.
Site in English: Topkapi
ところで。東京にある、私の行きつけのトルコ料理レストランをご紹介します。トルコ人の研修生の太鼓判つきのレストランです。
日本語サイト: トプカプ